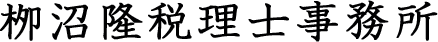今年の夏も相続税の申告終了と同時に仙台の街中にくりだし、藤崎ビアガーデンを何度も利用してビールをがぶ飲みして打ち上げしておりました。しかし、このビール業界にも酒税法改正の嵐が吹く日が近く来るかもしれません。
財務省は、ビール系飲料にかかる酒税の税額を統一し、ビールの定義も約110年ぶりに見直す方向です。ビールより税金が安い「発泡酒」や「第3のビール」の開発競争が過熱しておりましたが、ビールを減税して名乗れる対象も広げることで、海外で通用するビール開発につなげたいという考えだそうです。
1908年に麦芽やホップを使い、麦芽の使用比率は67%以上と法律で定めていましたが、オレンジピール(果皮)のような香料を使うことを認めて、麦芽比率も引き下げる方向で見直すようです。
ベルギービールなどはオレンジピールやハーブなどを使っていて、麦芽比率も50~67%が多いそうです。日本では発泡酒の扱いですが、麦芽が25%未満の日本メーカーの発泡酒と違って、ビールと同じ税金を払う規定になっておりまして、欧州連合(EU)が見直しを求めていました。
これらは「酒税法」における酒類の種類・品目という分類の違いによるものです。
まずビールと発泡酒の違いは、 ①麦芽使用率と②使用原料の二面から定められています。酒税法上「ビール」に分類されるためには、麦芽を原料の3分の2以上使用し、副原料
においても政令によって使用できるものが限定されています。(麦芽や麦、ホップ、米、とうもろこし、でんぷん等)
一方、発泡酒は麦芽使用率が3分の2未満、ビールとしては使用できない原料を使用している場合で、麦芽、麦を原料の一部とした発泡性を有する酒類とされています。
これに対して新ジャンルと呼ばれるお酒は、酒税法では「その他の醸造酒」あるいは「リキュール」に分類される酒類です。
麦芽、麦以外を主原料に使ったものは「その他の醸造酒」に分類され(サントリー商品では『ジョッキ生』があります。)、また、従来の発泡酒に麦由来のスピリッツや蒸溜酒などを加えた製品は「リキュール」に分類されます(サントリー商品では『金麦』があります)。
いずれも、各社、製法の工夫によって低価格ながらも、ビールに近い味わいを実現させるべく努力を重ねております。
年末にかけて与党やビール業界と調整し、来年度税制改正に盛り込むことをめざすようです。
税理士の立場からいえば、企業努力をもう少し認めてあげてもらいたいというのが本音です。