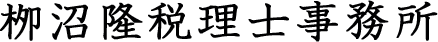第108話で最高裁の判決事例をご紹介しましたが、今回は、地裁・高裁・最高裁の大きな違いについて考えてみましょう。
日本の司法が三審制を採用していることはよく知られています。通常は地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の三段階で裁判が行われます(事件の性格によっては簡易裁判所、地裁、高裁の3段階で裁判を行うこともあります)。
しかし、地裁、高裁、最高裁で3回にわたって、同じような裁判を繰り返すわけではありません。以下、民事裁判について説明しますが、地裁、高裁で行われる裁判(下級審)は事実審、最高裁で行われるのは法律審であり、裁判の基本的な性格が異なります。
例えば、夫が知人の女性と朝まで一室で過ごし、それを知った妻が離婚を求めて裁判を起こしたとしましょう。下級審では、夫と女性の間で発生した事実をまず認定し、それが民法770条の定める離婚事由(「配偶者に不貞な行為があったとき」「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」)に該当するかどうかを判断し、判決を下します。これに対し最高裁では、下級審の事実認定は変更せず、その事実をもとに法律をどう適用すべきかを判断することになります。
下級審の判決に不服である場合、必ず最高裁に上告できるわけではありません。上告するには、判決の憲法解釈に誤りがあること、憲法違反があること、最高裁の判例とは異なる判断が下されたことなどの上告理由を満たしていることが必要です。高裁での控訴審で敗訴した側は、最高裁でも争って判決を覆すべく、これらの条件を満たす上告理由を書面に記入して提出しますが、ほとんどの場合は理由を満たしていないと最高裁に判断され、上告は棄却されて控訴審の判決が確定します。このため日本の裁判制度は「事実上の二審制」との見方もあります。
審理の状況も地裁・高裁と最高裁では異なります。最高裁は法律問題のみを扱うことから、ほとんどの審理は地裁・高裁から提出される書類に基づいて行われる上、民事訴訟法や刑事訴訟法は、「最高裁は一度も口頭弁論を開かずに上告を棄却することができる」と定めているため、上告の大部分(ほぼ全部)は一度も口頭弁論が開かれないまま棄却されます。従って、上告が受理されて口頭弁論期日が指定されることは、特に民事事件においては珍しく、逆に言えば、上告が受理され、口頭弁論期日が指定された時点で、高裁の判断が最高裁によって変更されたり、最高裁が従前の判例とは異なる判断をしたりする可能性が高まります。
ですから、第42話でお話しした通り、最高裁が「大法廷」を開廷する時点で。高裁の判断が覆されることが予想できるのです。