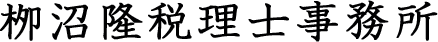非嫡出子(婚外子)がいるというだけ、普段から顔を合わせているような相続人にとっては、非嫡出子にも相続分を分け与えることは苦痛かもしれませんが、相続人であれば非嫡出子にも遺産をもらう権利があります。
こういったトラブルを避けるために、何ができるのかを確認しておきましょう。
例えば、男性が結婚後に配偶者以外の女性との間で子どもが生まれた場合などです。不倫や浮気でできてしまった子どもでも、父親が認知をすれば「非嫡出子」として相続人となります。
そのために、いざ相続する際に遺産分割協議(相続人全員で話し合いをする)を行うのが難しくなり、揉める可能性が高いことが容易に想像できます。
話し合いだけで解決をすれば良いのですが、相続手続きを進めている中、被相続人が亡くなられた後で「非嫡出子」の存在が発覚することもあります。急に出てきた法定相続人に、遺産を渡したくない人もいるのではないでしょうか。
その争いを避けるためには、被相続人が亡くなる前に「遺言書」を書き残してもらうのが一つの方法です。遺産の分割の方法を指定していれば、余計な話し合いをする必要はなくなります。
被相続人が生きている間に話し合いをして、法定相続人が誰であり、遺産に、どんなものが、どれだけ残っているのか確認をしておくことが重要です。誰が法定相続人になるか確認をしておくことで、「非嫡出子」の急な出現による混乱を回避できます。例え話し合いをしていくうちに、「非嫡出子」がいることが発覚しても、被相続人が生きていれば建設的な協議が可能です。
第103話から第105話で書いているように遺言書は公正証書遺言をお勧めします。
争いが起きてしまった際は弁護士に相談することをお勧めします。自分だけで悩んでいても、解決への道筋が見えてきません。そんな時は、多くの事例を経験している弁護士の力を借りるのが得策です。
ですが、弁護士に依頼をするうえで、どうしも費用が発生します。話し合いだけで解決をすればそれほど費用はかかりませんが、調停や訴訟までになりますと、ケースによってですが約50〜100万円程度は着手金等だけでかかります。
事件が終了した場合には結果に応じて追加報酬(請求金額の4〜16%が一般的)を支払うのが通常です。勝訴はしたが、手元にはあまり残らないケースもあることをご理解下さい。