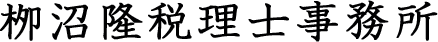~ 民事信託 ~
「信託」とつくと、信託銀行を思い浮かべる方も多いと思いますが、民事信託とは、平成19年9月の信託法の改正により、新しくできた信託の形で、信託銀行等のように、営業目的の信託のことを「商事信託」と呼ぶのに対して、営業を目的としない信託のあり方として生まれた信託を「民事信託」と呼び、その中でも、夫婦間や親子間での信託を「家族信託」と呼んだり、福祉を目的とした信託を「福祉信託」等と呼んだりしています。
「民事信託」は、商事信託と同様に、不動産を含む財産等を所有する人(ご本人)を委託者と呼び、委託者よりその財産等の管理・処分等を受託する人を「受託者」と呼びます。また、この「受託者」の管理・処分等の行為により、何かしらの利益(収益)や負担等を受ける人を「受益者」と呼びます。
例えば、土地・建物等の不動産を所有しているAさんが委託者となり、配偶者であるBさんを受託者として、ご自身を受益者とした場合、信託登記をすることにより、受託者のBさんは、Aさんのために、その不動産を購入したい買主と契約することができ、且つ買主より売買代金(手付金や残代金を含む)をAさんのために受領し、受領した売買代金は、Aさんのものとなります。
このような説明をすると、「なんだ、主旨としては、委任と変わらないじゃないか?」と思われる方もいらっしゃいますが、大きく異なる点は、委任の場合、確かに、ご本人に代わって売買契約の契約行為はできますが、万が一、決済時(前)に司法書士が、Aさんと面談し、意思能力に欠けると判断された場合、決済することができません。
ところが、民事信託を利用することにより、信託契約によって、管理・処分権がBさんに与えられていれば、例え、決済時等にAさんに意思能力が欠いているとしても、民事信託の契約時にAさんに意思能力が有り、且つBさんの意思能力に問題なければ、決済をすることができます。
また、民事信託は、遺言の限界を穴埋めする有効な制度の1つともいえます。遺言では、遺言者は自身の財産を「誰に、どの程度、相続させる(あるいは遺贈する)」と指定することができますが、そこまでが限界。例えば、ご本人(Aさん)が、特定の財産を「配偶者Bに相続させる。」とはできますが、「配偶者Bに相続させ、配偶者Bの相続時には、子Cに相続させる。」としてしまうと、「配偶者Bの相続時には、子Cに相続させる。」の部分は無効となります。
なぜならば、Aさん本人の相続時には、ご自身の財産なので、当然、その意思は、遺言により有効ですが、配偶者Bさんの財産については、あくまでBさんの財産(遺産)となるので、例えAさんの遺産により相続を受けた財産であってAさんの遺言書に記載があっても、Bさんの意思しか反映できないのです。
もちろん、Bさんが、遺言により当該財産を「子Cに相続させる。」という遺言を作成すれば別ですが、遺言は後から書き換え(正確には、後から作成する遺言にて抵触する部分を否定する。)することが可能なので、子Cとしては、Aさんの意思による将来的な財産の取得を保全することができません。
ところが、民事信託は、あくまで、遺言のような「一方的な意思」ではなく、双方、あるいは、各々による契約であるため、Aさんが、自身が亡くなった場合、その特定財産を配偶者Bの名義とし、さらに配偶者Bが亡くなった場合は、子Cの名義とすることが可能となります。
注意点としては、3つあり、1つは、遺言も民事信託もそれぞれ、作成時、契約時に本人の意思能力がしっかりしていることは必須であり、可能であれば、作成時、契約時には、医師の診断書を取得する事。
2つ目は、民事信託は、このような遺産分割の対策等としての利用は有効ですが、節税効果は見込めず、むしろ、不動産等においては、信託登記を行う必要があるため、登記費用を要します。
最後に3つ目として、民事信託という制度が、世に知られ、普及してきたのがここ数年ということです。しかも、相続実務を専門としている士業の中でも、民事信託を取り扱える方はごく限られた方のみであります。そのため、この、ほんの一握りを除いた各種専門家には、全く馴染みがないとうのが最大の問題点かもしれません。
実をいいますと私自身もこのような何世代にも影響が及ぶ民事信託の実務については、あまりの責任の重大さに幾分尻込みをしております。
しかし、「民事信託」を利用した相続対策は、「超最先端」であるため、そこを理解していただくのも一苦労ですが、誰かが門戸を開かなければ、この有意義な制度が活かされないため、士業を扱う一人としてこのような有意義な制度を、全国各地に広めていきたいと考えております。