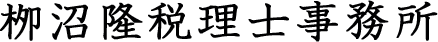借金も相続財産です。そして遺産分割の対象です。
しかし、積極的財産(プラスの財産)とは法律的に異なる扱いが一つだけあります。それは、法定相続分と異なる遺産分割協議内容が債権者に主張できないということです。
もう少し易しく解説します。
被相続人に、4000万円の現金と、2000万円の借金があり、遺言書はなく、相続人が子ども4人(A、B、C、D)だけだったとします。法定相続分で計算すると、子どもは、それぞれ現金1000万円と借金500万円を相続します。この内容で相続するのならば何の問題もありません。
しかし相続人は、協議により法定相続分と異なる遺産分割をすることができます。例えば、Aは借金を全部と現金3000万円、B、Cはそれぞれ現金500万円と借金はゼロ、Dは、借金も現金も相続しないという協議がまとまったとしましょう。相続人4人の合意があれば法律的にはこの協議は有効で、A、B、C、Dは、この協議内容に拘束されます。すなわち、Aが借金を払わなくても、B、C、DはAから「代わりに払ってくれ」という依頼に応じる義務はありません。
しかし、B、C、Dは、債権者(Eとします。)から、500万円(法定相続分)の借金を返済しろという請求に対して、これを支払う義務があるのです。もちろん、B、C、DのEに対する返済は、協議内容に反しますから、B、C、DはAに対して、それぞれ500万円の請求(求償といいます。)することはできます。
このようなことを法律的に、「協議内容は当事者(A、B、C、D)間で有効だが、債権者Eには対抗できない。」と表現します。
Aに資力がない(つまり積極財産を消費してしまうなど)と、B、C、Dは結局求償権があっても行使できず、Aが相続した借金の肩代わりをさせられることになります。
これに対応する方法は後ほど説明するとして、法律が何故このように規定しているのかを説明しましょう。
債権者Eは、借金を返してもらえるのであればだれが債務者になってもかまいません。でも債権者は、そもそも被相続人(亡くなった人)が返済してくれる人と思った(信用できると判断した)からこそ金を貸したのではないでしょうか?ですから、債権者Eは、信用できない人(借金を返してくれそうにない人)には相続してほしくないわけです。法定相続は「法律で決まっている」ので仕方がないが、遺産分割のように、相続人同士が任意に借金の相続人を決めてもらっては困るのです。このような事情で、借金の遺産分割は、債権者に対抗できない、ということになったのです。もちろん債権者が遺産分割内容を承諾すれば、債権者に対抗できるようになります(債権者が良いというのだから当然です)。
さて、借金を法定相続分とは異なる割合で遺産分割する場合の例に戻りましょう。次は対処方法の話です。
対処方法のひとつは既に説明済みです。それは、「債権者に分割内容を承認してもらう」ことです。これで、借金を相続しなかった人が返済を請求されることはありません(これを免責的債務引受といいます)。
債権者が承諾しない場合はどうでしょう。この場合は、借金は法定相続分どおりに分割し、トータルとして相続人同士で納得できる分割協議書を作成するのが一番です。どうしても借金を1人に相続させるのであれば、債権者が承諾をしてくれる相続人(債権者が信用している相続人)に借金を相続させるか、求償債務を負うべき相続人に対して何らかの担保(不動産抵当権、認諾文言付公正証書の作成等々)をとっておくのが良いと思われます。