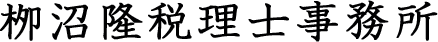第970話 特別受益

2023年度税制改正大綱で、生前贈与した財産を相続税の対象に引き戻す「持ち戻し」の見直しが盛り込まれました。この持ち戻しは正式名称を「生前贈与加算」といい、相続税法で定められた税金のルールです。
相続に関しては、民法においても持ち戻しのルールがあります。なぜ持ち戻しのルールが2つあるのかというと、これを説明するには相続税法と民法の違いを理解しなければなりません。
相続の際、専門家に遺産分割について相談すると「遺産分割上(民法上)は○○だけど、税法上は××になる。」といった説明を受けることがあります。
これは、基本的な相続のルールは民法による一方、税に関わるときは相続税法が民法を修正する規定を置いているためです。
民法では、相続の条文は882条以下にあります。
「相続は、死亡によって開始する」という条文から始まり、法定相続人の順位や相続放棄の方法、遺留分の計算方法など、相続に関するさまざまな決まりを置いています。
民法があるなら、相続税法は必要ないのでは?と考える方も多いかもしれません。
しかし、民法が決めているのはあくまで権利関係等の一般的なルールにすぎません。
税額の計算など、細かい税のルールについては相続税法の規定によることになります。
さらに、相続税法は、課税の公平性という独自の観点から民法に一定の修正を加えています。民法と相続税法は、別の趣旨で作られた法律なのです。
法律の世界では、一般法よりも特別法が優先するという原則があります。この民法の規定は、遺産分割がうまくいかず、裁判で揉めているにもかかわらず、相続税の申告期限が来てしまい、財産が未分割の状態で申告書を提出しなければならないときなどに使われます。そのような状態で持ち戻しを行う際には、相続税法にいう「生前贈与加算」の考え方ではなく「特別受益」のルールに従います。民法の規定による特別受益額の相続財産への持戻し計算をする場合の贈与財産の価額は、相続税法第19条《相続開始前三年以内に贈与があった場合の相続税額》及び同法第21条の15《相続時精算課税に係る相続税額》の規定による相続税の計算の場合と異なり、相続開始時における時価となるほか、税法の持ち戻しは現行で相続開始前3年以内、2023年税制改正で延長されても相続前7年の生前贈与に限られますが、民法には時効は存在しませんので期限の制限は一切ありません。何十年前の贈与であろうと、特別受益を主張した側がその存在を証明できれば、全額を相続財産に持ち戻しして遺産分割が行われます。
「2019年の民法改正で、特別受益には10年の時効が設けられたのではないか」と思われる方もおられるかもしれませんが、2019年の民法改正で時効が設けられたのは、あくまで「遺留分侵害額請求」の対象となる特別受益だけです。遺産分割協議の際に特別受益を主張するときは、何十年前の生前贈与であろうと持ち戻しの対象となる一方、いったん遺産の配分が決まってしまい最低限の取り分を請求するときには、直近10年分の贈与しか対象にすることはできないという意味です。
例えば、亡くなった父親が遺言で「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をしていたときなどが当てはまります。特別受益の持ち戻しは絶対ではなく、遺言で「持ち戻しをするな」と書いておけば行えません。しかし遺言で持ち戻しの免除をしていても、相続人の最低限の権利である遺留分を侵害することはできないため、遺留分請求はできます。ただそれでも持ち戻せるのは10年分に限るということになります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。