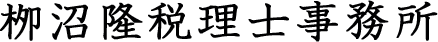第828話 小室母子から学ぶ「非課税所得」

以前、「佳代さんの遺族年金は不正受給ではないか」「圭さんは眞子様と結婚したら国連の職員になるのでは」と噂されたことがありましたが、この遺族年金と国連職員の給与は両方とも非課税扱いです。
非課税所得はメリットが多い反面、いろいろな問題もはらんでいます。非課税所得とは、社会政策などから「所得税や住民税を課税しない」と法律で定められたものです。
佳代さんの受け取る遺族年金は、公的年金に加入していた人が死亡した後、遺族に支払われるお金です。「遺族の生活保障に課税するのは酷」という観点から非課税とされています。
遺族年金の受給のハードルはそう高くはありません。しかし再婚・事実婚をすればすぐに打ち切りとなります。「前年の収入が850万円未満あるいは所得655万5000円未満であること」も条件となります。
一方、圭さんの就職先として噂された国際連合。ここから支給される給与にも課税されません。「国際連合の特権及び免除に関する条約」の他、所得税法においても非課税と規定されています。国際機関にはこのほか様々ありますが、皆同様の扱いです。
所得額が同じでも「課税」から「非課税」になったとたん、使える税制優遇の幅が広がります。税制優遇はたいてい「所得○○円以下」という所得制限がついていますが、この所得は「課税所得だけ」だからです。非課税所得は含みません。結果次のようになります。
(1)所得控除を受けるための所得条件
- 配偶者控除=合計所得金額が本人で1千万円以下かつ配偶者で48万円以下
- 配偶者特別控除=合計所得金額が本人で1千万円以下かつ配偶者で48万円超133万円以下
- ひとり親控除=本人の合計所得金額が500万円以下かつ子の総所得金額等が48万円以下
- 寡婦控除=本人の合計所得金額が500万円以下
- 基礎控除=合計所得金額が2400万円以下でなければ48万円控除できず
- 住宅借入金等特別控除=合計所得金額が3000万円以下か1000万円以下
非課税所得をもらう本人は、こういった控除を受けられません。控除は課税所得からしか差し引けないからです。しかし家族は使えます。
例えば「妻が国連職員で本人は会社員の場合」を考えてみましょう。
本人の所得が1000万円以下なら、妻の年収が1000万円超でも配偶者控除は受けられることになります。なぜなら妻の国連職員の給与は非課税扱いになり、合計所得金額がゼロになるからです。
それでは、今度は贈与の場合を考えてみましょう。
贈与税の非課税制度は、お金をもらう側の子や孫に対し、次の所得制限を設けています。
- 教育資金の贈与税の非課税措置=合計所得金額が1000万円以下
- 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置=合計所得金額が1000万円以下
- 住宅取得資金の贈与税の非課税措置=合計所得金額が2000万円以下か1000万円以下
留学や進学、結婚・出産といったイベントの際、年収1500万円の会社員だと、祖父母
からお金をもらっても所得制限を超えていますので課税されますが、しかし国連職員な
らば、非課税措置により合計所得金額が0となり贈与税は課税されません。
しかし非課税所得にはデメリットもあります。
非課税所得とされる収入は、遺族年金や国際機関からの給与以外にもありますが、い
ずれも法律ではっきりと指定されています。次の3つは、課税扱いとなります。
1, 相続税・贈与税・固定資産税など所得以外にかかる税金
2, 国連職員の退職金・年金にかかる所得税・住民税
3, 非課税所得以外の所得にかかる所得税・住民税
2.については、条約や税法が非課税所得としているのは、「国際連合が支払った給料及び手当」に限定していることによります。
非課税所得だけだと、国民健康保険税などの公的サービスも負担0です。非課税所得のメリットはかなり大きいといえましょう。
しかしそのメリットが大きくなればなるほど、それが人生の足かせとなります。公的負担に自腹を切るのがいやになれば、とうぜん就業や起業、結婚といった場面で選択が狭まります。
「佳代さんは以前、交際相手に『事実婚を内密に』とメールした」と、週刊文春が今年4月に報じましたが、支給停止が怖かったことにより、結婚の自由を奪ったとも見えます。
非課税所得には、古くに創設されて以降はほとんど改正されていないもの、趣旨を理解しがたいものがあります。遺族年金と国連職員の給与もその一つです。
遺族年金の非課税所得は明治20年の所得税法導入時から変わっていません。
当時は女性の就労は難しく、遺族年金は稼得能力の低い遺族の生活の保護に不可欠のものでした。受給額も葬祭費程度で、少額の遺族年金を非課税所得とするのは、政策として妥当だったのです。しかし今、女性は自由に仕事を選び、稼ぐことができます。他のシングルマザーの不平等の原因ともなっています。
国際機関からの給与は主権免税(自国で他の国から得た所得には課税しない)を根拠として非課税扱いとされています。しかし国際機関は国ではなく、一組織です。それにそれだけを根拠として一般人より高い給料をもらって課税所得が0など納得できるはずはありません。富裕層課税はもちろんのこと、非課税所得も見直す必要がありそうです。
戦後の日本の税制改革に貢献したシャウプ使節団の日本税制報告書の一文を紹介します。
「租税システムは公平でなければ成功しない。そして、納税者が公平だと認めるような租税システムでなくてはならない。」
果たして現在の税制は公平の課税と言えるのでしょうか?
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。