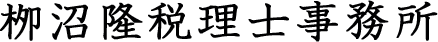第598話 最高裁における税務訴訟

被相続人が加入していた生命保険から年金が支払われるが、年金の現在価値に相続税が課税されたうえに、毎年の年金の支給額に所得税が課税されることに疑問を持った税理士が、これが二重課税になるという訴訟を起こしました。高裁では敗訴でしたが、最高裁で言い分が認められました。
「これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ、所得税法9条1項15号により所得税の課税対象とならないものというべきである(最高裁平成22年7月6日判決)」。
将来の受領額を年金原価の方法で割り引いた現在価値に相続税を課税しているのだから、将来、年金を受け取った場合においても、現在価値分は既に相続税を課税済みとして、差額(利息相当額)についてのみ所得税を課税するという理屈です。
このように最高裁が納税者側を勝訴させることがあります。ただし、最高裁は実務に影響を与えない事件でしか納税者を勝訴させないのが通常です。つまり2度と発生しない事件でしか納税者を勝訴させないことになります。ところが年金訴訟では納税者を勝訴させました。いったいなぜなのでしょうか。
相続財産とは、被相続人が所有していた財産に限るのであって、生命保険金は相続財産ではありません。生命保険金は民法537条の第三者のためにする契約に基づく支払であり、保険会社から直接に受取人に対して支払いが行われます。
仮に契約者の死亡時に、妻に5千万円支払う旨の契約を保険会社と締結し、契約者は保険会社に毎月の保険料を支払います。そして契約者の死亡時には、その妻が保険会社から5千万円の保険金を受け取る形になります。保険金は、妻が契約者から承継する相続財産ではなく、保険会社から支払われる金員という扱いになります。なので、本来ならば妻の一時所得になるべき収入なのです。しかし生命保険金は、その実質からして相続財産と差異はありません。そこで「みなし財産」として相続税の課税対象に取り組んでいます。
本来ならば一時所得(所得税)の課税対象ですが、それを相続税の課税対象に取り込んでいるのだから、その後、保険金が支払われた段階で所得税を課税したら当然二重に課税されることになります。その理屈は、保険金が一時金で支払われた場合も年金で支払われた場合も変わりありません。
最高裁は納税者を勝たせたいのが本音です。もし、当事者の主張を公平に判断していたら、全ての事案で課税庁が勝訴してしまいます。課税庁は更正処分の段階で判断し、再調査請求で判断し、審査請求で判断します。つまり、地方裁判所は税務判断については4番目であり、高裁は5番目、最高裁は6番目となります。納税者側を勝たせることは、税法のプロである国税庁が組織的に判断した結論を、税法については素人の裁判官が覆すことに他なりません。そしてその結果は、その都度全国一律で行われている税務行政を変更させることになります。そのような恐ろしい判断ができる裁判官がはたしているのでしょうか。
しかしそのような臆病な実務に浸っていたら、すべての税務訴訟で国側勝訴の判決になってしまいます。ほとんどの事件で検察の主張を認め、有罪判決になるのと同様に、国税側の主張を全て是認していたら、裁判など必要ないと批判されかねません。
そこで最高裁は実務に影響を与えない事件で納税者を勝利させることにしました。つまり2度と発生しない事件です。バブル処理で問題となった興銀事件、税法改正直前に駆け込みで行われた武富士事件。これらの事案で納税者を勝利させても、その理屈が将来の実務に適用されることはありません。しかし、年金訴訟の判決は実務を変えてしまいました。
その理由は平成22年2月に税務大学校の税大ジャーナルに掲載された「生命保険をめぐる相続税法および所得税法上の諸問題」と題する論文に原因があります。この論文では、年金訴訟について、国の主張が間違いであり、課税処分を取り消すべきであると論じております。課税庁のシンクタンクである税務大学校が自ら課税の間違いを認めるのなら、最高裁がその理屈を採用しても不思議ではないし、むしろ採用すべきともいえます。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。