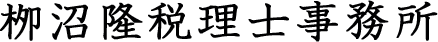第1081話 金還付スキームに対する当局の対応

令和6年度税制改正で、金取引に関し、新たな消費税の制限が設けられることとなりました。具体的には、消費税を納める義務がある課税事業者が、1年度中に200万円超の金を仕入れた場合、その仕入年度から3年間は消費税の免税事業者になれず、簡易課税の選択もできなくなります。従来、1回の取引単位として、1千万円超の金を仕入れていればこの制限が発生するとされていましたが、取引単位ではなく1年度で200万円としたことで、広くこの制限に抵触することとなります。
金取引に関する消費税の税逃れといえば、数年前まで行われていた金還付スキームが思い出されます。これは金取引を数回繰り返すことで、本来還付されない居住用賃貸建物の消費税の還付を受けられるというスキームです。このスキームは令和2年度改正でブロックされていますので、今回の改正はこれと異なる、新しい金取引の節税をブロックする税制改正と思われます。
実際、どのような節税が問題視されたのか、考えられることの一つに、課税事業者である期間中に大量の金を仕入れ、免税事業者になった後にその金を売るという仕組みが考えられます。こうすれば大量の金を仕入れた年度で多額の仕入税額控除を受けられる一方で、免税事業者になれば消費税が課税されませんのでいくら売っても消費税を納税する必要はありません。
改正前の制度においても、課税事業者がその翌期から免税事業者になる場合、上記スキームを行っても消費税は還付されませんでした。しかし、これも消費税の抜け穴なのですが、課税事業者として金を仕入れた後、その翌々期から免税事業者になれば、この制限は発生しません。加えて、翌期以降に免税事業者になれなくても、売るタイミングで簡易課税を選択すれば、金の売却額に対する消費税を節約することができます。
実際にこのようなスキームが行われていたのかはわかりませんが、金取引に対してこのような改正が行われるのであれば、3年間は課税漏れが発生しませんので、おそらくはこれらの点を考慮したものと解されます。
ただし200万円程度の金取引でもNGとなると、善良な納税者が余裕資金で金を運用するような場合も問題になるわけで、そうなると金取引の前にこの制度が問題になるかどうかを税理士はチェックしなければならず、ただでさえリスクが大きい税理士業務について、また面倒な問題が生じることになります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。