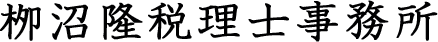第1073話 国VS地方 差し押さえ争奪戦
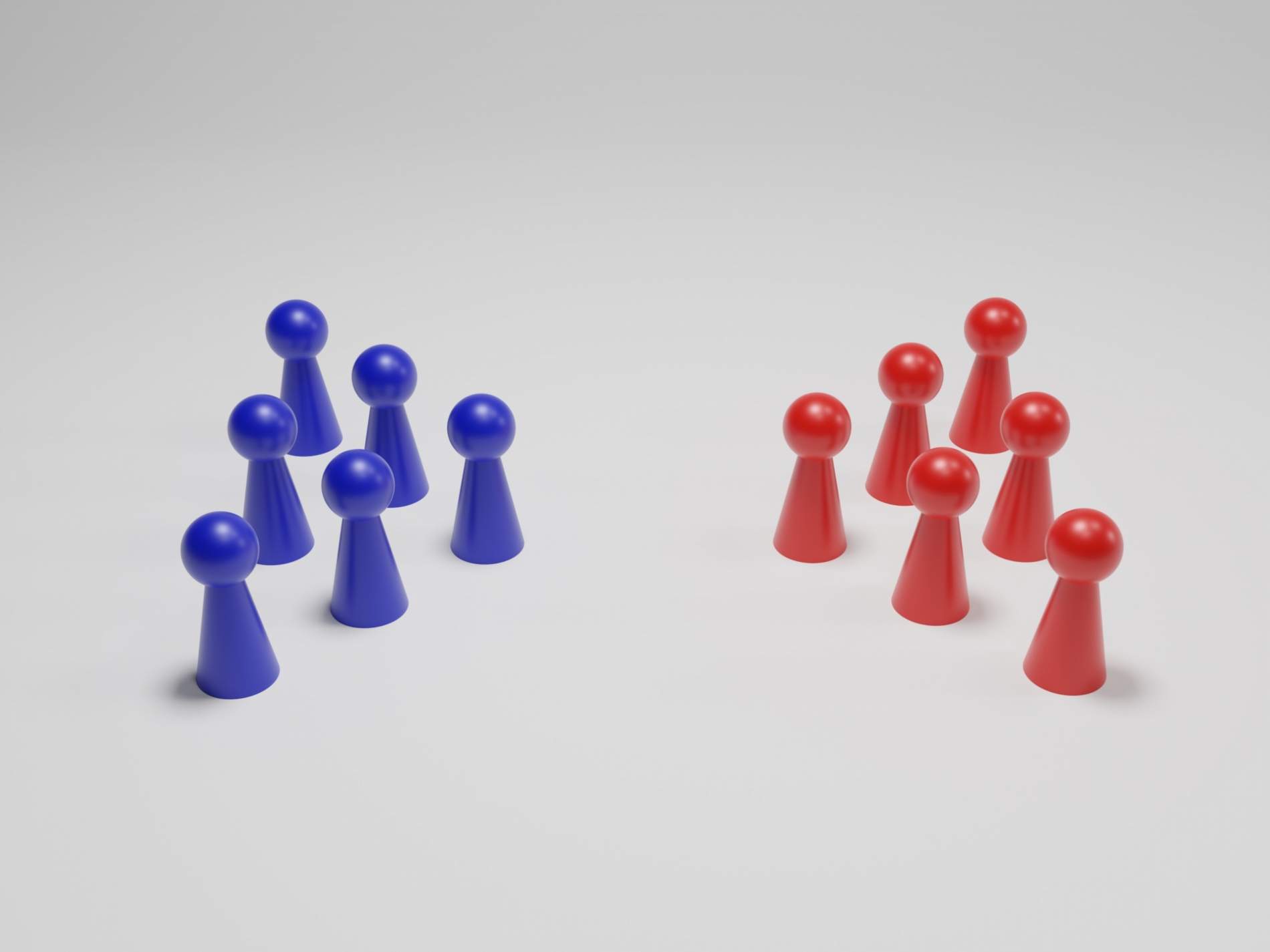
国税でも地方税でも、督促に応じない滞納者が後を絶ちません。こうした滞納者が現れたとき、その財産の差し押さえに動くのが双方の徴収部門です。財産の差し押さえに当たっては、早いもの勝ちが基本です。滞納していた会社の倒産時には、滞納者の限られた財産を巡って、国税と地方税の仁義なき戦いが繰り広げられます。
国税徴収法8条では、「国税は、すべての公課その他の債権に先だって徴収する」と国税優先の原則を定めています。かたや地方税法14条にも「地方団体の徴収金は、すべての公課その他の債権に先だって徴収する」と地方税優先の原則が定められています。それでは、国税と地方税の徴収が競合したときはいったいどうなるのでしょうか?
これについては、国税徴収法では「滞納処分である差押または交付要求の着手時期を基準に先だって徴収する」としています。交付要求とは、滞納者の財産について、すでに強制換価手続が執行されている場合に、競売の売却代金から未納金を回収するため、執行機関へ滞納税等の配当を請求する手続きをいいます。つまり原則として先に差し押さえるか、または交付要求書を提出した方が勝ちということです。
そのため徴収の現場では「国」対「地方」のバトルが繰り広げられることになります。
特に両者が先を争うのは、滞納していた会社が倒産したときです。差し押さえる財産が不動産であれば「差押の登記」が早いほうが優先されます。同じ日付でも法務局の受付順で勝負が決まるため、それぞれの徴収担当者は大急ぎで法務局の窓口に駆け込みます。そして財産が動産であれば占有が優先されます。つまり、差押物件を証明する専用標識を貼って封印をした順になります。
差し押さえで双方の徴収官が慌ただしく駆け込むのは法務局に限りません。銀行も差押のレースの重要な場所です。向かった銀行で徴収官は一般客とは別の部屋へ案内されます。もしレースに敗れると、早速差押手続きを開始しようと思った矢先に、行員から「すでに市役所(もしくは税務署)さんが…」と告げられ、一歩遅れていたことに肩を落とすことになります。
はっきり言ってスピードの勝負ですから、両者が急げば、現場で国税と地方税の担当者がバッタリと出会う場面も出てきます。お互いに目があえば会釈はするものの、闘志を抱くのも致し方ありません。
差し押さえの現場での国税と地方税の戦いは、一昔前は国税の圧勝でした。以前の地方税の徴収部門は国税に比べて徴収ノウハウが未熟で、行動力で劣っていました。これは、地方公務員には自治体の中での異動が度々あるためです。せっかく徴収技術を身に付けても2年程度で税金担当から異動することも少なくありません。そうなると人は育たず、経験による徴収ノウハウはなかなか後任に引き継がれませんでした。
また地方は納税者との距離が近く、滞納者が滞納整理担当職員の知り合いというケースも珍しくありません。しがらみから職務に没頭できない場合もあるようです。
ただしこうした事情も過去のものとなりつつあります。各地方自治体は徴収率アップに必死に取り組み、成果を上げてきており、いまや国税とがっぷり四つに組み合うまでになってきています。
地方が変わるきっかけになったのが、税収格差の是正を目的に行われた小泉政権下の「三位一体の改革」です。これは「地方にできることは地方に」という理念のもと、国の関与を縮小し、地方の権限や責任を拡大して地方分権を推進することを目指し、国庫補助金負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体として行った改革です。
このうち、税源移譲とは、国民が国税を減らし、地方税を増やして、国から地方へ税源を移すことを言います。この税源移譲を行うことにより、国に基づく多くの規制があった補助金に比べて自由に財源を使えることができます。反面、地方は国から半自動的に交付されてきた財源を自らの力で集めなければならなくなりました。
これにより地方自治体は必死に改革を進めざるを得なくなり、徴収率を上げるため、国税に協力を求めてレクチャーを受けたりしました。国税当局の担当者に講師を依頼し、地方の職員に滞納整理について教授してもらい、徴収技術を伝え合う「情報交換会」を定期的に開催したそうです。そうした努力の結果、国税とも対等に渡り合えるになってきました。
改革の積み重ねによって異動の際も一定のノウハウは引き継がれるようになってきています。地方税の担当者は、今や実力では国税の担当者に能力的に劣りません。今この時にも国税VS地方税の戦いが繰り広げられています。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。