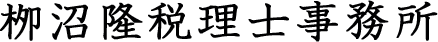第910話 総則6項

実勢価格と相続税路線価の乖離を利用した節税手法の是非を巡って納税者と国税当局が争った裁判で、最高裁は4月19日に、国税当局の言い分を全面的に認める判決を下しました。税法上は合法であっても当局が税逃れとみなせば否認できる、いわゆる「総則6項」の適用は合理的だと判断したのです。判決では総則6項の明確な適用基準は示されず、今後は土地だけでなく、自社株の評価などに広く適用される可能性も出てきました。
裁判の内容を詳しくみてみますと、争われたのは、原告側が相続で取得したタワーマンションの相続税評価額の正当性です。2008年、当時90歳だった被相続人が、信託銀行に相談して相続対策をスタートさせました。翌09年には、信託銀行から約10億円を借り入れ、2棟のマンションを計14億円ほどで購入しました。融資時に銀行が作成した内部稟議書では「相続対策のため」と記載されていました。その3年後に被相続人は死亡し、2棟のマンションは相続財産となりました。購入した時の時価は前述通り14億円ほどですが、相続税路線価では3億円ほどとなります。さらに購入にあたっての借入金を債務として控除した結果、2棟のマンションの相続財産の正味の財産価値は0円となります。相続人がこの路線価に従い申告したところ、当局が「路線価による評価は適当ではない」としてこれを否認し、約3億円を追徴課税した事例です。
こうした実勢価格と路線価の乖離を利用した節税策は「タワマン節税」と呼ばれ、多くの富裕層が相続税対策に活用してきました。しかし近年では、当局は積極的にこれらの税務処理を否認し、追徴課税をしています。
このとき当局が否認の根拠として使うのが、相続税の財産評価のルールを定めた財産評価基本通達の総則の第6項、いわゆる「総則6項」です。同項では、通達によって評価することが「著しく不適当」と認定できるケースに限り、「国税庁長官の指示を受けて評価する」と規定しています。評価ルール全体における例外規定とも呼べる内容で、この項目を適用すれば最終的には国税側の言い値が適用されることになります。
総則6項は、いわば何でもありの規定であるため、適用にあたっては国税内部でもハードルを設けています。それによると
①その財産について通達に定めがあること
②その定めによって評価するのが著しく不適当であること
③国税庁長官の指示があること
④通達以外の合理的な評価方法が存在すること
に当てはまるケースです。このうち②の「通達によって評価するのが著しく不適当」であるかが適用の可否を分ける分岐点であり、その判断基準について過去の判例では、租税負担の公平を著しく害することが明らかなどの「特別な事情」が必要としています。今回の裁判でも、納税者側の相続税対策がこの「特別な事情」に当てはまるかが争点となりました。
下級審にあたる東京地裁判決では、マンションの鑑定評価額と路線価の著しい乖離、税負担の軽減を意図した経緯などを踏まえ、「特別な事情」にあたると認定しました。二審の高裁判決でも、実際に鑑定評価額と路線価に大きなギャップが生じている事や相続税対策として実行されていることなどの事情を総合的に勘案して「特別の事情」に当てはまると判示しています。
下級審では路線価と実勢価格とのギャップがあること自体が「特別な事情」と判断する要素となると認定しましたが、最高裁は価格の乖離がただちに特別な事情にはつながらないとし、その上で、「近い将来発生することが予想される相続において、相続税の負担を減じ、又は免れされるものであることを知り、かつこれを期待して、あえて購入・借入を企画実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行った」ことを重視し、それが「他の納税者との間に見過ごしがたい不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する」ので、「特別な事情がある」と認定したとしています。総則6項を適用する為には実際に税負担が軽減しているだけでなく、あらかじめ税逃れの意図をもって行われたことが必要であるとして、当局にも一応の釘を刺したかたちです。
今回の件で「最高裁のお墨付き」という金看板を得た当局が総則6項を今後乱発する恐れも否定できません。
さらにオーナー企業の経営者にとって危惧すべきは、総則6項が適用されるのが土地だけではなく、自社株評価にも適用される点です。
昨春に、光学機器メーカー「HOYA」が、元経営者の相続に絡み約90億円の申告漏れを指摘されました。問題とされたのは、相続した自社株で、評価額が不当に低いと認定されました。同社は評価通達に従い自社株を評価し申告しましたが、当局は税額を不当に軽減させる行為があったとして総則6項を用いて再計算し、当初申告額の5.5倍の株価を採用しました。
過去にも、2014年には住宅建材大手のトステムが創業者の相続をめぐり、資産を不動産管理会社の自社株に変えて申告したところ、否認され60億円の追徴課税がされました。また2016年には精密機械メーカー「キーエンス」が、自社株を社債に転換するなどして評価額を低く抑えて相続税の申告をしましたが、国税に否認されています。さらに2019年には、教育関連書籍「中央出版」も、自社株を通達に従い算定したところ、否認されて60億円の追徴課税がされています。これらはいずれも総則6項の適用によるものです。
しかし判決で総則6項がこのように適用されるのならば、私たち税理士は、「財産評価基本通達」をどのように位置付ければよいのでしょうか。
今回の裁判で原告側は、時価の評価方法を定めた路線価を大きく上回る価額を採用することは、相続税法22条で定める「財産の価額は時価で行う」という規定に反すると述べ、当局の処分を批判しています。しかし判決では、「評価通達は時価の算定方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達に過ぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見つからない」と退けています。
法律を文言通りに解釈するならばおっしゃる通りの結論ですが、実務を生きる私たちにとっては、通達が実質的に法律と同じ拘束力を持っていることは、税に関わったことのある誰もが知っています。
税には、憲法84条で定められた「あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする」という『租税法律主義』の大原則があります。ですが通達は法律ではないため国会で議論が尽くされることはなく、いわば密室で当局が決めたものがそのまま発遣されます。そして現場では法律と同じように強制力を持って運用され、無条件に従うべきものとして採用されることが多くみられます。
執行上の様々な細かいルールを法律に全て定めることが非現実的である以上、通達が多用されるのがやむを得ないとしても、もし今回の裁判のように通達に法律的根拠がないことを判決理由にあげるのなら、租税法律主義の大原則をより徹底することが求められます。取引価格のない非上場株式のようなものの評価をするのに通達が一方的に計算ルールを決定して、財産的価値を強いているような現状において、司法の方から「国民に対する拘束力はない」と言われても、納税者は到底納得できないはずです。
今回の判決により、納税者が納税額を予見できないという問題がより深刻になり、国税の恣意的な課税にブレーキがかからなくなることは必須です。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。