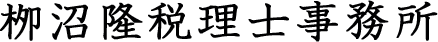第874話 生前贈与

昨年12月に決定した2022年度税制改正大綱では、かねてよりささやかれていた贈与税の年間110万円の非課税枠に関する見直しは盛り込まれませんでした。とはいえ話が立ち消えになったわけではなく、「本格的な検討」を引き続き進めると大綱では明記されています。今後、生前贈与を使った相続税対策はどのように変わっていくのか、これまでの経緯を振り返りながら考えてみましょう。
「今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」
昨年12月に公表された2022年度税制改正大綱で、この一文を読んでほっと胸をなでおろした資産家の人達も多かったのではないでしょうか。この文章で「本格的な検討を進める」とあるのは、贈与税の暦年贈与で認められている年間110万円までの非課税枠についてです。今回の大綱でその見直しが先送りされたということは、資産家にとっては毎年110万円の非課税枠を使った贈与による資産移転を用いた相続税対策の定番手法が存続したことを意味します。
そもそも贈与には大きく分けて「相続時精算課税」と「暦年贈与」の2種類の方法があります。
前者は、生前に贈与した分が2500万円まで贈与税がかからず、相続時に贈与当時の時価で相続税がかかるという制度です。土地などの価格が低いときに贈与しておき、いざ相続時に地価が上昇していれば大きな節税効果を得ることができますが、逆も起こりえますので博打的な要素も含んでいます。なにより最終的に相続税で生前贈与分が清算されるので、課税の繰り延べ制度であって非課税ではありません。最大の節税効果を生む人は、そもそも贈与分を相続財産に加算しても相続税がかからない人で、それ以外の人は、贈与時の価額を相続財産に加算することによる時間差による価格変動の差の節税のみとなります。
一方の暦年贈与は、年間110万円までの贈与が非課税となります。例外として死亡3年前までの贈与については相続財産に繰り入れられてしまいますが、それ以外は110万円までの贈与は、すべて非課税です。制度としてもシンプルでわかりやすく、資産家でなくても祖父母が貯めこんだ資産を孫に移す際などに広く使われてきました。
しかし、このあって当たり前の節税対策に異変が生じたのが2018年12月に決定された2019年度与党税制改正大綱です。そこでは贈与税の在り方について「いわゆる『老々相続』が過大となる中で資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築が課題」だとして、今後検討を進めていく旨を示しました。同様の内容は、翌年の大綱にも盛り込まれています。さらに2020年度税制改正に先立つ11月に、政府税制調査会が「暦年贈与は資産移転の時期の選択に中立的でない」、「制度の在り方を見直し、格差の固定化を防止しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制を構築する方向で、検討を進める必要がある」との見解をまとめたことを発端に、暦年贈与の在り方についての議論が再燃し、当時の甘利明自民党税制調査会長がすかさず「海外ではいつ資産を移転しても公平な制度がある。国際標準に極力沿う形にしていきたい」と同調したことから、がぜん暦年贈与課税制度の見直しの現実味が増しました。最終的に2021年度大綱でも暦年贈与の見直しは盛り込まれませんでしたが、大綱には「現在の税率構造では、富裕層による財産の分割移転を通じた負担回避を防止するには限界がある」、「資産移転の時期に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」と明記され、検討のギアが上がったことは明白でした。この年の大綱に30以上ある検討項目の中で「本格的」とされたのはここだけで、それだけに昨年末にまとめられた2022年度大綱でついに実現するのではないかと予想されていたわけです。
ところが例年であれば大綱の内容が取りざたされる秋になっても、暦年贈与に関する内容に触れられることはなく、12月10日に公表された与党大綱においても暦年贈与についての見直しはありませんでした。かわりに検討事項として記載されていたのが「本格的な検討をすすめる」という文言です。
なぜ2020年の時点で「本格的に」と書き加えてまで前のめりの姿勢を示していたにもかかわらず、今回の改正で暦年贈与の見直しが盛り込まれなかったのか。
その最大の理由として考えられるのが、時間がなかったことです。昨年は9月から10月にかけて自民党総裁選、衆議院選挙と政権運営に関わる大きな選挙が相次いだこともあり、税制改正の議論にかけられる時間は例年に比べて非常に短すぎたなかで大綱に掲げていたような「格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築」という大きなテーマをまとめることができませんでした。年間110万円の非課税枠を廃止するとなれば納税者からの反発も予想され、そこを納得させるための〝地ならし〟をする時間もなかったとみられます。
そしてもう一つの理由として考えられるのが、暦年贈与の見直しが社会全般に及ぼす影響が、当初想定していたよりもはるかに大きかったことです。
世の中には、対価を伴わない金銭のやりとりは数多く存在しています。そうした細かい金銭のやりとりに一つずつ課税するのは現実的でないため、相続税法では「原則として贈与を受けたすべての財産に贈与税がかかる」としながらも、いくつかの例外措置を設けています。
例えばお葬式の香典や年始のお年玉など「社会通念上相当と認められるもの」につきましては非課税ですし、夫婦間や親子間のお金の融通、祖父母が出す孫への教育資金など「通常必要とされるもの」についても非課税です。
ですがそれでも多くの個人間のお金のやりとりはこうした例外に必ずしも含まれず、非課税かどうかはグレーゾーンということも少なくありません。そうした細かいお金のやりとりをまとめて非課税扱いにしているのが、他ならぬ暦年贈与の110万円の非課税枠です。暦年贈与がある限りは、お金のやりとりの性質や相手、契約書の有無にかかわらず「年間110万円までなら税金はかからない」と簡単に判定することができます。
もし仮に暦年贈与が廃止されたなら、今までグレーゾーンであっても110万円以下なら問題なく非課税だった様々な金銭のやりとりが、いちいち「贈与税の対象になるのかならないのか」の判断を余儀なくされてしまいます。納税者にとっては非常に面倒であり、国税当局にとっても税額数万円のやりとりを一つ一つチェックするのはあまりに非現実的です。つまりは暦年贈与の廃止は、相続税対策封じにとどまらぬ大きな影響を社会全体に及ぼすことになります。
こうした予想を裏付けるのが、甘利明前自民党税制調査会長の発言です。甘利氏は暦年贈与の見直しについて過去に「見直しによってどういう問題が出てくるのか、そのシュミレーションをしているところだ」と発言しています。見直しの影響が大きく、そのシュミレーションに時間を割いていることが、2022年度大綱に盛り込まれなかった大きな理由である事が分かります。やはり数年内に何らかの動きがあることが予想されます。
では今後、生前贈与を使った相続税対策はどうなるのか。少なくとも生前贈与の非課税制度については縮小ないし廃止が既定路線であることは間違いありません。
さらに2022年度大綱には、「経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家庭内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、その在り方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ不断の見直しを行っていく必要がある」との記載があります。ここにある贈与税の非課税措置とは、教育資金、住宅取得資金、結婚・出産・育児資金のそれぞれに設けられている特例を指します。それぞれ数百万円から数千万円までの一括贈与が非課税になるものですが政府はこれらの特例について何らかの税負担を求める方向で見直しを行っていく姿勢です。早ければ次の税制改正で全面廃止される可能性もあります。
そして暦年贈与の廃止については、段階的に行われることも考えられます。例えば廃止の前段階として生前贈与の持ち戻し年数を3年から5年~10年ほどに延長する案が考えられます。持ち戻しとは、相続発生前の一定期間内の生前贈与については相続財産に戻して相続税を計算する方法です。こうして生前贈与の効果を薄めたうえで、最終的に制度そのものを廃止するのかもしれません。もっとも最終的なゴールが暦年贈与の全面廃止であることに変わりはありません。
相続税対策の中でも暦年贈与は難しい条件もなく完全非課税になる唯一とも呼べる資産移転の手段でした。しかしその最強の相続税対策は数年内に使えなくなるでしょう。最短で2023年度改正に盛り込まれ、早ければあと1年でなくなることを踏まえて残り少ないチャンスをしっかり活用してもらいたいものです。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。