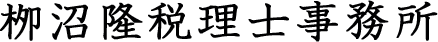第999話 認知症

高齢化が進む日本は、いまや世界でもまれにみる認知症国家です。経済協力開発機構によると、日本人が認知症を患う確率は2.33%で、先進国の平均(1.48%)を大きく引き離してワーストとなっています。2012年に462万人だった65歳以上の認知症患者数はすでに600万人を超え、2025年には730万人、2030年には830万人に達する見通しです。この数字は、高齢者の4人に1人の発症を意味します。広島大学の研究報告によると、コロナ禍で他人との交流や活動量が減った影響により認知症患者の症状が悪化している傾向も確認されています。
認知症患者の増加に伴い、相続トラブルも増加傾向にあります。認知症を発症すると、自分自身の思考能力が低下して適切な判断を下せなくなるだけでなく、法律上でも権利が制限されて有効な契約を結べなくなり、財産管理や相続対策、事業承継といったあらゆる法律行為が手詰まりになる恐れがあります。これは認知症により本人に一定の判断能力がないとみなされれば、発症後に結んだ契約は無効になってしまうことによります。
認知症であると判断されますと、預貯金の解約や不動産売買、相続などの手続きが制限されます。その際は「法定後見人」を利用して、本人に代わって法律行為を行う後見人を決定する必要が生じますが、法定後見人は本人や家族ではなく家庭裁判所が決めることになるので、選ばれた後見人によっては、本人や家族の意思にそぐわないような不動産管理や預貯金の解約、介護保険手続きなどが行われてしまうこともあります。
また法定後見人が本人に代わって財産管理や契約をするうえでは本人の資産維持を最優先しなければならないという制約があることから、帳簿上で本人の財産を減らしてしまう生前贈与や株式譲渡などの相続税の生前対策は基本的にはできなくなってしまいます。
法定後見制度を活用する手続きとしては、まず親族らが家庭裁判所に法定後見制度の利用を申し立て、家庭裁判所が判断能力の不十分な人に代わって財産管理や契約行為を行う法定後見人を選任します。法定後見人は本人の財産や立場を維持する役割があり、本人の財産や生活の状況を定期的に家庭裁判所へ報告する義務を負います。法定後見人には裁判所の実務に慣れた弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門家が選ばれやすく、2022年度に親族が法定後見人として選ばれた割合はごく一部にとどまり、これら専門家が80.9%と多数を占めています。法定後見人がひとたび決定されますと、原則変更はできません。被相続人が会社の社長であった場合は、問題はさらに複雑になります。
弁護士や司法書士は、企業経営に直接携わってきたわけではないため、的確な経営判断が下せる保証はどこにもありません。しかも法定後見人は家庭裁判所の監督下におかれますので、株主総会で議決権を行使するときなど、スピーディな対応も難しくなります。法定後見制度は従来から使い勝手の悪さが指摘されており、政府は見直しに着手するといっているものの見通しはまだ立っていません。
結局のところ、認知症が相続に及ぼすリスクを最小限に抑えるには発症前に対策を講じておくしかないことになります。その対策としては、日常生活で必要な契約や財産管理の代行者を選任する「任意後見制度」、財産の管理・運用・処分に特化して委任する「信託契約」、財産管理を第三者に委任する「財産管理契約」の3つが挙げられます。
1つ目の「任意後見制度」で代行者となった任意後見人は、法定後見人と同様の権限が与えられ、住居の確保や医療・介護の手続きなど、日常生活に必要な契約を本人に代わって行うことができます。裁判所が決定する法定後見人とは異なり、任意後見制度では裁判所ではなく本人が選定できるのが大きな違いです。
さらに公正証書による委任契約で定めておけば、本人の生活上必須なものにとどまらず、様々な手続きを任意後見人に代行してもらえます。例えば任意後見人に「自社の保有株式の議決権を行使する権限」を委任しておけば、任意後見人の議決権行使に本人の意思を反映できるようになります。
しかし、任意後見人は法定後見人と同様、本人の財産保護を第一義に求められるため、株式の運用や自宅の売却といった財産の運用・処分は原則として行えません。
そこでこれらをカバーする手段が「信託契約」です。信託とは、信頼できる家族や専門家に財産管理を任せる契約を言います。この契約は、任意後見制度のように財産の運用や処分に対する縛りがないため、信託を受任した人が財産を柔軟に活用できます。信託契約には、家族と契約を結ぶ「家族信託」と信託銀行のような専門機関と契約を結ぶ「商事契約」の2種類があります。同じ信託でも、任せられる財産の範囲や費用などが異なります。
家族信託のメリットとしては、信託する財産や方法など契約内容を当事者間で自由に決められる点が挙げられます。任意後見制度で禁止されている相続税対策を目的とする不動産の売却や資産運用のための株式の購入も可能となります。信託は原則として契約を結んだ時から効力が発生するため、受託者に財産の管理権が移動してしまいますが、「認知症になったら信託を開始する」などの条件を盛り込んだ「停止条件付信託契約」を結んでおけば、認知症になるまで信託する財産を自分で管理しておくことができます。
受託者には、委託者の信頼を裏切らないよう、常識人として財産管理に配慮する「善管注意義務」や委託者の要望に応える「忠実義務」、委託された財産と自分の財産をしっかり区別して扱う「分別管理義務」などが課されます。受託者は帳簿の作成・保存を行う必要があり、これらの決まりを守らなければ、契約違反に伴う民事責任が発生し、損害額の賠償責任や原状回復の義務を負います。家族信託は財産管理の自由が保証されているものの、委託者の意思を無視して悪用できないように一定の規制が設けられています。
一方、専門機関と契約を結ぶ「商事信託」では、多額に上る信託財産の運用をプロに任せられるという安心感がある反面、委任財産の種類が原則制限されます。また信託銀行に対しては報酬が生じ、財産の規模によって額は異なりますが、相談料や着手金など契約成立に係る費用だけで100万円を超えることも珍しくありません。さらにランニングコストも生じます。
これらの信託契約は、あくまで信託財産の管理のみを委任する契約に過ぎないので、本人の日常的な契約行為を代行する権利は持ちませんので、認知症を発症した後に施設入所や医療など日常生活のサポートをしてもらうためには別途、認知後見契約を結ぶ人をあらかじめ決めておかなければなりません。
また信託財産として名義を変更した財産以外の管理・運用・処分は任せられないので、どの財産を誰に任せるのか、相続人同士の不公平感を生まないためにも、慎重に検討する必要があります。
3つ目の対策として活用されている「財産管理契約」は、本人の財産管理を家族や知人などに任せる方法です。この方法は手軽に財産管理を任せられますが、管理する財産や代理権の範囲、管理の方法といった契約内容については契約当事者同士で決定できる点は家族信託と同じですが、登記手続きの代理はできませんので、不動産の売却などは受任者単独では行えません。金融機関からの預貯金の引き落としなどについても、金融機関の規則次第では代理が認められないケースもあります。
認知症患者は民法上「意思能力のない者」と判断されて契約行為が無効になる恐れがあるので、相続プランが総崩れになるリスクがあります。預貯金の引き出しや解約、生命保険への加入、不動産の売買、生前贈与、養子縁組、遺産分割協議といった様々な法律行為が自分の意思でできなくなります。
また相続対策をするうえで何より問題なのが、認知症発症後は原則として遺言を残せなくなる点です。認知症患者が作成した遺言は直ちに無効にはなりませんが、医療記録や介護記録、遺言の内容、筆跡の乱れなど様々な観点から遺言を残した時点で意思能力があったかなかったかを家庭裁判所がチェックします。過去の判例を見ますと、認知症患者の遺言については厳しい判断が下されています。
例えば1998年の東京地方裁判所の判決では、被相続人の認知症の進行度合いについて関係者間で意見が割れたものの、精神知能検査の結果や医師の診断、遺言書の文章の稚拙さなどを踏まえて遺言が無効とされています。また2016年の東京地裁判決でも、認知症と診断されていた被相続人が残していた公正証書遺言について、認知症専門医の意見書や証人尋問の結果から、遺言を書き残した当時も遺言能力がなかったとして無効とされています。
遺言が残せないとなれば、遺産の配分については相続人同士の話し合いである遺産分割協議で決めることになります。認知症対策を怠ってしまいますと、これまで講じていた相続税対策や事業承継プランが総崩れになりかねません。あらゆる事態を想定して、認知症対策に取り組む必要がありそうです。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。