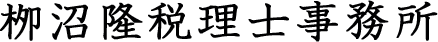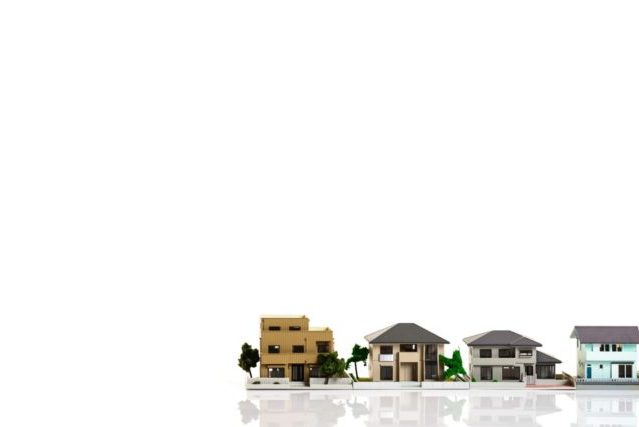所得税
第1078話 相続税取得費加算の特例
相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を3年10カ月以内に譲渡した場合、支払った相続税額のうち、譲渡した財産に相当する相続税額を譲渡資産の取得費に加算することができます。例えば当該相続人が相続した財産が…
続きを読む第1003話 空き家の譲渡特例
今年度の税制改正では、空き家の譲渡特例に関して大きな要件緩和がなされました。空き家の譲渡特例とは、相続した空き家について、一定の要件を満たしたうえで売却した場合、所定の要件を満たすことでその譲渡所得から3千万円の控除が…
続きを読む第966話 固定資産の交換の特例
土地や建物などの取得には原則として譲渡所得税がかかりますが、固定資産を同じ種類の固定資産と交換した時に限っては、その譲渡がなかったものとする「固定資産の交換の特例」が利用できます。ただし、この特例を受けるためにはいくつ…
続きを読む第828話 小室母子から学ぶ「非課税所得」
以前、「佳代さんの遺族年金は不正受給ではないか」「圭さんは眞子様と結婚したら国連の職員になるのでは」と噂されたことがありましたが、この遺族年金と国連職員の給与は両方とも非課税扱いです。 非課税所得はメリットが多い反面…
続きを読む第812話 店舗併用住宅
先日、たまたま夜7時に日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』を見ていたら、2階が自宅のお店は安くてうまいという情報を得ました。 このように1階を店舗として使い、2階に自宅を構えて住んでいる中…
続きを読む第811話 不動産の交換
土地や建物などの譲渡には原則として譲渡所得税がかかりますが、固定資産を同じ種類の固定資産と交換した時に限り、譲渡がなかったものとする「固定資産の交換の特例」を利用することができます。ただし、この交換特例を受けるためには…
続きを読む第805話 不動産共有名義の注意点
マイホームや投資不動産について、夫婦の共有名義で購入することは珍しくありません。これは税制面からみますと、非常に節税効果が高い購入方法です。 例えば不動産投資で、持っている物件が事業的規模であるならば、2人分の青色申…
続きを読む第802話 親族相盗
災害や盗難などの予期せぬ被害を受けた時には、「雑損控除」という被害者救済のための措置が使えます。「差引損失額-総所得金額等×10%」か「差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のうちいずれか多い方の金額を所得から…
続きを読む第800話 家政婦
家族の誰かが入院することになったとき、夫婦共働きの家庭であれば、24時間の付き添いが難しいので、病院での世話のために家政婦さんを雇って介護を依頼することがあります。このようなときに家政婦に支払った費用は、医療費控除の…
続きを読む第789話 老人ホーム入居者の自宅売却
マイホームを売った人は、譲渡所得から最高3千万円までを控除できる特例を適用できます。この特例の適用要件は、自分が住んでいる家屋を売るか、または家屋と共にその敷地や借地権を売ることです。ただし、売却時に住んでいた家屋でな…
続きを読む第788話 相続した賃貸不動産の計算方法
まず耐用年数からご説明します。通常、事業用の中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、使い始めた時以降の「使用可能期間」を見積もって算出することが認められています。しかし相続で取得した中古資産の耐用年数については、そ…
続きを読む第763話 マイホーム~名義の登記~
配偶者の一方だけが仕事をしている家庭であれば、マイホームの名義を働く人のものとしても何の問題も生じませんが、共働きの夫婦の場合には課税上の問題が生じることがあります。具体的には、共働きの夫婦で妻がマイホームの資金の一部を…
続きを読む第762話 マイホーム~住宅ローン返済中でも家を貸す方法~
基本的には住宅ローンの返済中に家を賃貸に出すことは出来ません。最初から賃貸を目的に家を購入するには賃貸住宅向けのローンを組むのが通常です。一般の住宅ローンを組んだ銀行に内緒で賃貸しようものなら、そのことがバレた時にはロー…
続きを読む第761話 交換特例
転居や結婚、または事業の開始などの理由により親戚同士で資産を取り換えるということはよくあることです。例えば自分の持っている空き地と近隣に暮らす兄が所有する宅地を交換したとします。この時に気になるのが譲渡所得税ですが、固定…
続きを読む第672話 男はつらいよ 第4作 新男はつらいよ
第4作『新男はつらいよ』での話です。 名古屋に出張したタコ社長は、競馬場で寅さんとばったり出くわします。寅さんは大穴馬券を買っていました。その馬の名前はワゴンタイガー。「ワゴンは車、タイガーは虎。早くいやぁ車寅次郎…
続きを読む第667話 5棟10室基準
不動産の貸付規模が、税務上の「業務」か「事業的規模」によって、税金面でのお得さは大きく変わってきます。 例えば不動産所得は家賃収入から必要経費を差し引いて計算しますが、事業的規模と認められますと青色申告の対象者は一…
続きを読む第658話 土地の交換
ある地主が、ゼネコンの委託業者から「土地の交換には税金がかからない」とアドバイスを受け、ゼネコンに土地を譲渡して別の土地を取得したところ、業者の説明は誤りで税務署から追徴課税を受けた事例があります。地主はゼネコンに責任…
続きを読む第621話 所得税法59条と60条
相続にも所得税法が登場します。仮に土地を子が親から相続で取得した場合は、子は父親の土地の取得価額と取得時期を引き継ぐことになります。これが所得税法59条と60条の理屈です。 相続や贈与による資産の移転には、相続税や贈…
続きを読む第577話 終活リフォーム
人生で最も高価な支出は税金といえそうです。そして次点につけるのが、多くの人の場合は住宅でしょう。そこで人生100年時代、老後の生活資金を切り詰めなくては生きていけないこのご時世、あの手この手で工夫が必要になります。 …
続きを読む第552話 住宅ローン控除
日本の25歳から34歳の若年層が親と同居している率は42%で、世界7位という結果があります。親孝行という見方もできますが、一方親としては自立を促したいという思いもあるでしょう。 逆に、子供が自分名義でローンを組んで家…
続きを読む